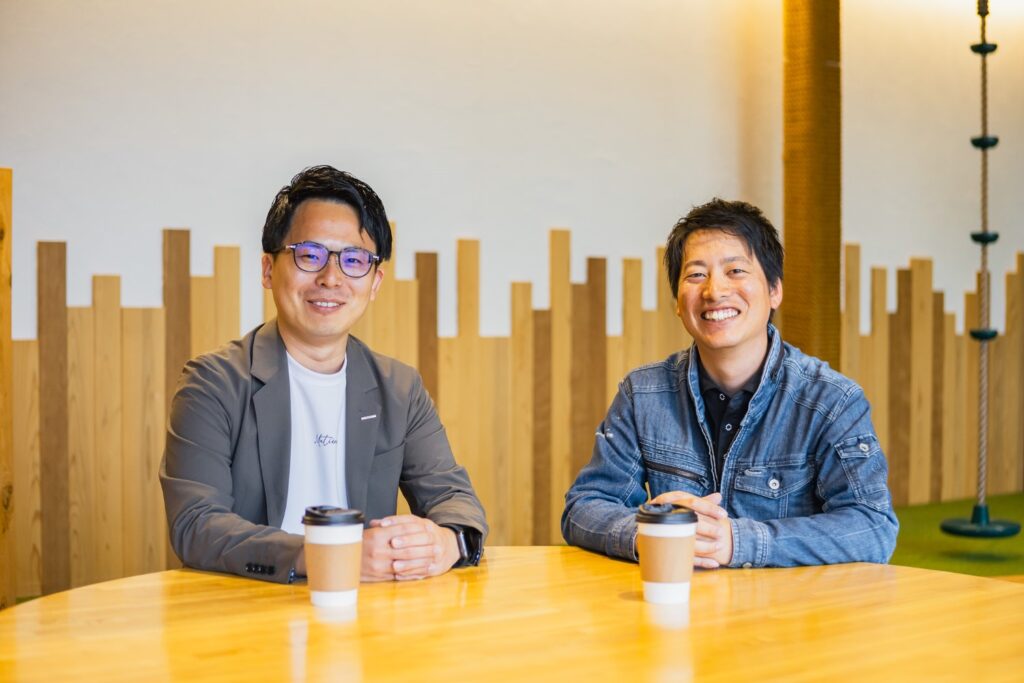SAWAMURA PRESS

SAWAMURA高島本社に、元パタゴニアで、愛される企業を増やす活動を進めているfascinate代表の但馬武さんが来てくださいました。「愛される企業になるためにはどうしたら?」「リーダーに必要なことは?」等、ふたりが語り合った内容の後編です。
前編はこちら:はたらくことに「ワクワクすること」が必要な理由
https://www.sawamura-shiga.co.jp/sawamurapress/sawamurapress-2438/
目次
チャレンジを褒めるのは、いつも「社外」の人から
ファンがいる企業は、どうやってつくられる?
SAWAMURAが高島でコワーキングスペースをつくりたい理由

但馬武さん
パタゴニア日本支社にてダイレクトマーケティング部門統括を中心に19年勤務。2019年2月に熱狂的なファンを創り出していくfascinate株式会社を創業。「愛される企業 Lovable company」の創出のために企業理念から事業創出、マーケティング戦略構築などに年間10社ほどに伴走している。
チャレンジを褒めるのは、いつも「社外」の人から
澤村:但馬さんは「愛される企業」というコンセプトでワークショップを開催したり、企業に伴走することも多いと思うのですが、そういったときに反発は受けませんか?
但馬:愛される企業とは顧客から愛されることを意味しているのですが、そのための活動を生み出すにはやっぱりそこで働くスタッフが企業を愛していないと難しいです。なので、私の専門はマーケティングではありますが、組織づくりから入ることが一般的で、まずはその組織のことを教えていただくためのヒアリングやワークショップに多くの時間を取ります。
その会社の置かれている現状やマーケットの環境を見れば、戦略ややるべきことをイメージすることはあまり難しくありません。しかし外部の私が思っているだけではダメで、社内の皆様が「よしやるぞ!」にならないと、自分たちの取り組みになっていかないんです。
だから僕はセッションを重ねて、企業の存在意義や今後の未来についてみんなで対等に話し合うムードをつくる。そうしている中で、少しずつ会社の雰囲気が変わっていく。そのプロセスが大切だと思っています。日本においては儒教の影響が強いので、対等に話すことが難しいんですよ。
澤村:今のお話、すごくわかります。僕たちも今、企業としてジャンプアップするために、外から先生のような方に来てもらって、いろいろ教えてもらいたいと思うんですよ。でも心配なのが、その行為自体が、社内の人を否定しているように受け止められるのではないかということ。つまり「君たちができないからこの人に教えてもらうんだよ」というメッセージにならないかどうか。本当は、議論のファシリテーターとして社外の人にいてほしい、というだけなのですが……。
但馬:イノベーター理論というものがありますよね。もともとはマーケティング業界で活用される言葉ですが、何かしら変化が起こるのには順番があり、最初に採用する人がいてそれに追随する人がいて、というステップを理論化したものです。その中で、最初に飛びついて取り組みを開始する「イノベーター」的な人は全体の約2.5%しかいないんです。
これは組織づくりにおいても同じことが言えると思います。つまり企業の変容においても、まずやってみる人は2.5%くらいだと思って取り組むことです。100名の企業であれば2−3名と始めてみる。そしてその取組がイノベーターからアーリーアダプター、アーリーマジョリティーに広がっていく。やっぱり時間がかかりますよ。組織の中でチャレンジはなかなか理解されません。理解してもらい、普及させるまでが大変です。
澤村:たとえば誰かが会社で新しい画期的なチャレンジを始めたとき、最初にそれに気づいて評価するのは、社内の人ですか、社外の人ですか?
但馬:圧倒的に、社外の人ですよ!
澤村:えっ、そうなんですね。

但馬:どうしても自分のやっていることは過小評価するもので、それは組織であっても同じだなと思います。社外の人から評価されて初めて、社内の人が「あれ? 結構すごいことやってるのかも?」と理解する。でもこれは企業に限らない話ですね。たとえば、禅のような思想は、日本では当たり前のものとされていた。でも海外で評価されて初めて、マインドフルネスという言葉で再輸入されていったじゃないですか。やっぱり社内の人間は、自分のやっていることの価値に気づきにくい。
たとえば今日僕は高島にやってきて、「なんて素敵な田園風景なんだろう」と感動しました。が、毎日見ている皆さんにとっては、きっと普通の日常風景にしか見えませんよね。それは仕方がないことです。やっぱり外部の人に褒められないと、価値に気づかない。
澤村:たしかに……! 僕、学生時代の同級生に仕事でまちづくりをしてると言うと、「なんで?」と首を傾げられるんですよ。地元や故郷を肯定することが恥ずかしくなってしまう感覚が彼らのなかにはあるのかなと。そもそも日本全体で、自分たちがやっていることや住んでいる場所を誇る行為は恥ずかしい、という感覚があるのかもしれない。企業も同じかもしれませんね。
但馬:私が愛される企業だと思っている長野・松本に本社を構える藤原印刷の話を共有させてください。長年にわたる印刷不況のなかであっても、業績が素晴らしく、「藤原印刷さんに印刷してほしい!」とわざわざ顧客が松本に訪ねてくるような会社なんです。そうなっているのは、印刷をする会社という枠組みを超えて、表現活動に伴走する会社だと自社をリフレーミングできているからだと分析しています。
藤原印刷に依頼した顧客は印刷の現場を立ち会うのですが、そのときに営業担当のみならず工場の現場スタッフとも対話を行うんです。そのときに顧客は彼らの技術の高さをみて感動するわけです。さきほどの話にもありましたが、社内の人からの祝福は少ないですし、あったとしても社内からのフィードバックはどこか受け取りづらい場合があります。しかしながら、顧客からのフィードバックは効果てきめんです。印刷する職人さんたちも、外部の方からの直接的な祝福はやっぱり嬉しいし、やる気が出る。
いまでは藤原印刷では、年に1回工場を開き、印刷過程や技術そのものを見せるイベントを開催している。それによって、会社の空気が変わっていったそうです。SAWAMURAさんももしかしたらそのような設計が必要な時期かもしれませんね。
澤村:実は以前、同じようなことを言われました。社内で「働きがい」を調査するアンケートがあって、この数値を上げるためにどうしたらいいか、ある人に相談したんです。すると「SAWAMURAさんの取り組みはすごいんだから、もっと第三者に褒めてもらう機会を増やしたほうがいい」と言われました。今の但馬さんのお話を聞いてみても、第三者に褒めてもらえてはじめて得られる自信ややりがいがあるんだな、と痛感しました。
但馬:僕がワークショップで組織変容プログラムを行うとき、いつも同じようなことを言います。「スタッフは、会社の上司よりも、会社のお客さんに褒められたほうが嬉しいんだ」と。みんな、組織変革というとすぐ社員の評価システムについて考えてしまう。けれど、重要なのは、外部からのその企業に対する声なんです。
僕が「企業のファンづくりが大切だ」とよく言うのは、会社を評価してくれるお客様が増えたほうが、結果的にスタッフのやりがいにもなるから。ファンの数が増えるとスタッフが喜ぶ。事業作りだけではなくファン作りが重要だと思うのは、そこが理由です。

ファンがいる企業は、どうやってつくられる?
澤村:愛される企業とは、どうすればできるんでしょうね。
但馬:僕が愛される企業について考えるとき、いつも感じるのが「ひとは強さで頼られ、弱さで愛される」という言葉です。
どうしてもぼくらは強さを意識してしまいがちで、弱さはダメだと思ってしまう。しかし弱さとは、他者の優しさを引き出すものなんです。弱いからダメなわけではない。弱さは、他者のスキルや能力を引き出すことができる。実際にぼくらが誰かを愛おしく感じるのは、強さではなく弱さに触れたときではないでしょうか。しかし組織の中では、特に男性はつい強くなろうとしてしまう。なかなか弱い本音を言葉にできない。日本の企業にも「弱さはむしろ他者の強さを引き出すツールだから、ちゃんと言葉にしていいんだ」と言ってあげるのがすごく大切だなと感じます。
澤村:たしかに、パワフルな男性は、営業戦略を引っ張ったり新規事業をつくりだしたりする場面では優れていますが、企業の課題を整理したり組織開発を考えたりする段階に至るとなかなかまとまるのが難しい。結局、聞いてくれる人がいないと、意見の整理ができない。それは結局、どうなるかわからないような、まだ弱さのある言葉を喋るのが苦手だからかもしれない。
但馬:企業で考えてみると、強さについてこい!と言われるよりも未完成であることを怖れず、できないことも受け止めながらも、でも自社が願う未来について表現していく。それが伝わって「この会社を応援していくことが、自分が想像する未来に繋がっていくんじゃないかな」と思ってもらえる。完璧さよりも、未完成でも、弱さを見せてでも、願いを共有し一歩踏み出そうとすることを見せるのが大切。その姿勢に、共感が生まれファンができる。
澤村:そうすることで他者が応援する余地ができる、ということですね。
但馬:最近では企業でも町づくりでも、ファンベースのような形が増えている、と僕は思うんです。たとえば、長野の諏訪市にある「ReBuilding Center JAPAN(リビルディングセンタージャパン)」。ここは古材や古道具を扱うリサイクルショップなのですが、創業当初から仲間内のみならず多くのサポーターの支援によって事業が拡大していってます。そればかりでなく、諏訪のまちはリビセンができたことによって多くの人が集まり、使われなくなっていた商店街に活気が出てきている。
この5年でリビセンがリフォームを手掛けたお店以外も加えて30店舗が新たにオープンしているんです。そのうちのいくつかは、リビセンの代表夫婦の友人やファンたちが店舗を始めているケースもありますし、インスタグラムでの投稿を見て移住してきた方もいらっしゃいます。
「自分たちで全部はできない、でもこうなったら楽しいよね」を共有し、そこに共感する人が一緒に行動してくれる。このようなファンベースの作り方みたいなものが、今後の日本における事業展開のひとつのヒントになるのではと。
澤村:SAWAMURAでも、先日「旧高島町の空き家を、コーヒーとコワーキングと本のある空間で、共創が生まれる拠点を作る」というプロジェクトで、クラウドファンディングを実施しました。地域にかかわっている個人の方々とのつながりを密接にしていきたい、という気持ちがすごくある。それもファンベースの試みかもしれません。

SAWAMURAが高島でコワーキングスペースをつくりたい理由
但馬:コワーキングスペース、すごくいいですね!池袋にあるマテックス株式会社では、使われなくなったスペースをHIRAKUというコミュニティースペースに変え、そこでこれからの時代に必要な読書会や勉強会を開催しているんです。その場所は、地域のおじいちゃんやおばあちゃんたちのコミュニティの場としても利用してもらっている。そうすることで、勉強会に参加してくれる方々と、地域のコミュニティに参加してくれる方々を混ぜて触発することができるんです。
澤村:すごく面白いですね! まさに僕たちがやろうとしていることは、高島でコワーキングスペースをつくりだすことで、地方で活躍しているクリエイターや異業種の人たちが集まる場をつくりたいんです! 高島でコミュニティとなる場を設計したい。だからこそ今回コワーキングスペースづくりをやってみるんですよ。
但馬:まさに、SAWAMURAさんには設計施工の枠にとらわれず、地域づくりや町づくりのデザインまでしてほしい。例えばトヨタだって最初は繊維の会社だったし、マツダも最初はコルクの会社だった。企業はずっとひとつの産業で留まらなくちゃいけないわけではないんです。
御社の流れを聞いていると、建物を建てるだけではなく、そこに集う人々の営みも含めてデザインしていくようになるのでは? と感じます。「ゆたかな暮らしをデザインする」という言葉であれば、事業面では建物や家をつくることになるし、社内に目を向けてみると社内制度やスタッフエンゲージメントを高めるワークショップをつくることになり、その経験はまち全体のブランディングプロセスをデザインすることにも活かせますよね。もちろんこれは一例ですが、御社の役割を表現する言葉もリフレーミングするタイミングなのかもしれません。
澤村:今、会社の将来像を見せる言葉が必要になっている、ということですね。たしかにそこをしっかり整理しないと、どこかで「設計施工の会社」という役割にとらわれてしまいそうです。そうなると次のステップに行けなくなってしまうな。
但馬:先ほどお伝えした藤原印刷さんも、もちろん印刷会社なので印刷することが仕事という定義でしたが、新しい顧客が増えていくにつれて徐々に「自分たちの仕事は表現したい人を支援する会社なんだ」とリフレーミングしていくことになりました。現在、藤原印刷さんは、表現したい人の相談に最初から関わり、印刷という枠を超えて伴走をしています。そうやって企業は変化し、変化の先に新しいチャレンジや新しい達成があるからこそ、顧客に信頼されていきます。いくつかのお仕事でご一緒していますが、本当に素晴らしい企業ですし、他の方にも真っ先にご紹介するのが藤原印刷さんです。まさに愛される会社だなあと思います。
澤村:たしかに。社外にも、社内にも、どちらにも自分たちの価値を伝えていく言葉をつくることが大切ですね。とくに社外の声を社内に伝えていくような取り組みは、今後さらに伸ばしていきたいなと今日思いました。自分たちの価値を自分たちで言葉にして認めていくことが、社員の自信にもつながっていくのだな、と。
但馬さん、今日はすごくいいお話を聞けました。本当にありがとうございました!

前編はこちら:はたらくことに「ワクワクすること」が必要な理由
https://www.sawamura-shiga.co.jp/sawamurapress/sawamurapress-2438/
この記事を書いた人
 |
三宅香帆 |
Interview&Text:三宅香帆/Edit:SAWAMURA PRESS編集部