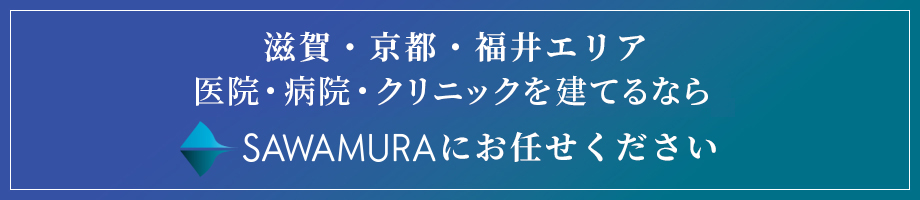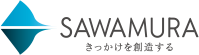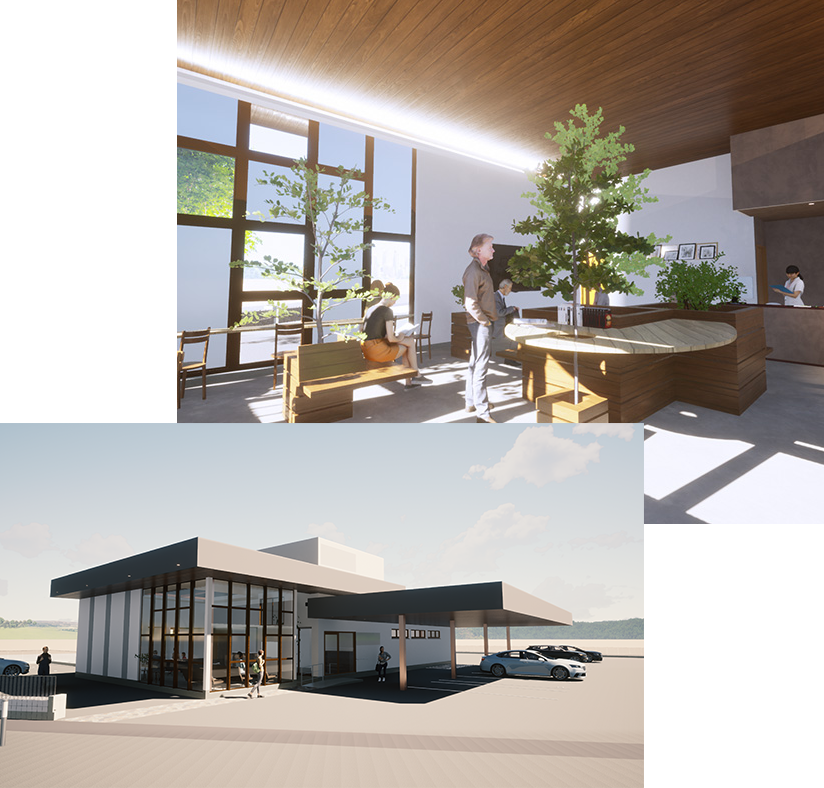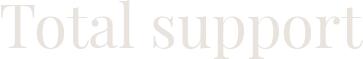最終更新日:2023年03月20日
医療施設や福祉施設を建てるにあたり、知っておかなければならないのが「特定建築物」です。
利用者の安全性を確保した建物を建てるためには、建築基準法に基づいていることが重要。その際に知っておかなければならないのが、特定建築物という言葉とその意味です。また、特定建築物と似たものとして「特殊建築物」も存在します。
今回は、特定建築物の概要や、特殊建築物との違い、建物を建てる際の注意点などについて幅広く解説します。
特定建築物とは
特定建築物とは、建築基準法6条1項目一号に該当する建築物もしくは法令で定められた建築物のことです。特定建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関連するものであり、医療施設や福祉施設のほか、博物館や美術館図書館、百貨店など多くの利用者が想定されるさまざまな建築物に該当します。また、延べ面積は3,000平方メートル以上であることが特定建築物にあたります。
特定建築物と特殊建築物の違い
特定建築物と特殊建築物の違いとして、まず挙げられるのが法律の違いです。特殊建築物は、建築基準法の2条1項二号に規定される建築物のことであり、学校や体育館、劇場、展示場などのほか、火葬場や汚物処理場、と畜場などが該当します。
しかし、2016年に施行された法改正に伴い、定期報告が必要な建物に限り、特殊建築物ではなく「特定建築物」と呼ばれるようになりました。
ちなみに、定期報告とは、「定期(調査)報告制度」のことで、建築基準法によって義務とされている報告のことです。安全面や防火、衛生面の確保が重要とされる建築物に課せられた義務であり、この義務が課せられている建物が特定建築物に該当します。具体的には、病院や有償診療所、就寝用福祉施設、サービス付きの高齢者住宅、有料老人ホームなどが挙げられます。
特定建築物を建てる際の注意点
特定建築物を建てるにあたり、いくつか把握しておくべき注意点があります。
思わぬトラブルを防ぐためにも、特定建築物を建てる計画を立てている方は参考にしてみてください。
本当に特定建築物なのかを確認する
まずは、特定建築物を建てる前に、建築を計画している建物がそもそも本当に特定建築物であるのかを確認しましょう。特定建築物と特殊建築物では、延べ面積や建築物の特徴などに違いがあります。いずれも似たような言葉であり、建築に関する法律が関わっていることから、勘違いしてしまうことが少なくありません。
建築計画の段階で正しい方向性を定めないと、いざ計画を詰めてから改めて計画を立て直しすることにもなりかねません。手間増やすことにならないよう、きちんと建築物の種類を確認しましょう。
まちづくり条例を確認する
特定建築物を建てるにあたり、確認したいのが地域のまちづくり条例です。まちづくり条例の内容によって、建築に規制があります。まちづくり条例は都市を中心に施工されていることが多いので、主要都市に特定建築物を建てようと検討している方はとくに注意しなければなりません。
まちづくり条例に関する問い合わせ先は、建築を検討している市区町村の役所です。「建築指導課」「福祉課」などで情報が得られるので、建築計画を立てる際には、問い合わせておくと安心です。
必要な届け出を確認する
特定建築物の建築を計画する際には、どのような届け出が必要となるのかを確認しておきましょう。特定建築物に限らず、建築物を建てる際には何らかの届け出をしなければならず、手間がかかるもの。特定建築物はさらに、「特定建築物使用(該当)届」の届け出が必要となるので忘れないようにしましょう。
ちなみに、特定建築物使用(該当)届の期限は、使用(利用)を開始する日から1か月以内です。忘れてしまうことのないよう、早めに届け出を出しておくことをおすすめします。
関わる法律を理解する
特定建築物を建築する際には、どのような法律が関わるのかを正しく理解する必要があります。一般住宅であってもさまざまな法律を守ったうえで建築されています。特定建築物の場合はさらに関わる法律が多く、その分確認事項も多いので注意が必要です。
なお、特定建築物に関わる法律は以下の通りです。
・建築基準法
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律(バリアフリー法)
・建築物のエネルギー消費性能に関する法律
・建築物の衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)
特定建築物は主に4つの法律に関わるうえに、法律ごとに特定建築物の定義も異なります。
専門家のアドバイスも視野に入れながら、正しく理解できるよう努めましょう。
おわりに
特定建築物は特殊建築物と混同しやすいうえに、さまざまな法律が関わることから複雑な印象を持たれる傾向にあります。しかし、基本をおさえることで、特定建築物の正しい理解が深まります。
本ページを参考にしながら、安全な特定建築物の建築計画を進めていきましょう。